今回は吉田修一さんの「国宝」を読んだので話の伏線などについて解説します。
今年(2025年)6月6日から吉沢亮さん主演、横浜流星さんの共演の映画が公開されますね、そちらも楽しみです!
「国宝」は歌舞伎の世界を題材にした人間模様を描いています。
上下巻なので結構ボリュームはあると思うかもしれません。
さらに伝統芸能の話なので、難しくて読みにくいのかな と おもいきや
これね 面白い!!
普通に生活していると知る事のない世界、長さを感じることなくサックサク読めちゃいます。
新聞連載だったからか、時間の経過がわかりにくいところと話が急に違う飛んでいく感がありますが
慣れたら何も問題なくいけました。
Contents
粗あらすじと個人的な感想
物語のながれ
1964年元旦、長崎は老舗料亭「花丸」――侠客たちの怒号と悲鳴が飛び交うなかで、この国の宝となる役者は生まれた。男の名は、立花喜久雄。任侠の一門に生まれながらも、この世ならざる美貌は人々を巻き込み、喜久雄の人生を思わぬ域にまで連れ出していく。舞台は長崎から大阪、そしてオリンピック後の東京へ。日本の成長と歩を合わせるように、技をみがき、道を究めようともがく男たち。血族との深い絆と軋み、スキャンダルと栄光、幾重もの信頼と裏切り。舞台、映画、テレビと芸能界の転換期を駆け抜け、数多の歓喜と絶望を享受しながら、その頂点に登りつめた先に、何が見えるのか? 朝日新聞連載時から大きな反響を呼んだ、著者渾身の大作。
引用:朝日新聞出版
役者として生まれたわけではない名前も知られていない少年がガンガン成りあがっていく。
その行く末にあるのは栄光なのか挫折衰退なのか。
それは読んでのお楽しみ♪
そんな「国宝」
今回考察するのは下記の「5つ」です。
1.誰を中心としてみるか
2.最大のキーマン
3.女性陣の強さ
4.こまかい描写が想像を膨らます
5.個人感想
1.誰を中心にみるか
「国宝」はいわゆる大河小説という事で人生が描かれています。
歌舞伎の世界の話という事とタイトルから「人間国宝」の話なのかな と察しをつけて読み始めました。
中心的な人物は長崎の任侠「立花組」立花権五郎の血統をひきつぐ「喜久雄」、そして歌舞伎界「丹波屋」花井半二郎の血統をひきつぐ「俊介」。
喜久雄と俊介は世代が同じで出会いの時はお坊ちゃま同志ぶつかったものの、一緒に育っていく中でお互いに良い刺激になる関係性になっていきます。
芸のキャリアで言うと、15歳で歌舞伎に飛び込んだ喜久雄と幼い頃から仕込まれてきた俊介の差はあって当たり前。 ですが
これが思ったより早く埋まっていき喜久雄が頭角を現してきます。
強い芯がありながらも周りにはそう見せずに黙々と物事をこなしモノにしていく喜久雄は超美形の女形、人間的な弱さを底に持ちながら(たぶんね)も芸という面で飛びぬけてくる俊介は内面から女がでる女形になっていくのです。
しかししかし すべてが順調に進むわけがなく、両方ともに暗い穴が待ち受けてます。
かたや表舞台から姿を消し忘れ去られた存在になってしまい。
もう片方は表舞台にいながらも干されていく事で下っ端同様の扱いを受けつづけるようになり、それぞれが時期は違えど屈辱と挫折を味わう地獄期間となります。
とてもそこから巻き返せない状況としか思えないなか
はたしてふたりはどう這い上がってくるのか?
もしかしたら「国宝」となるのは思っているのと違う方なのか? と つい考えてしまいページが進みます!
このあたりは今後の展開が気になってもう目が離せなくなります!
後半に行くにしたがって「そうきたか!」と思わずニヤリとしてしまいました。
伏線も結構細かく張られてたなと思いました。
あーこういう意味だったんか みたいな事が結構ありました 笑
喜久雄が背負った「ミミズク」が最後まで喜久雄を象徴することになる事
万菊という大御所女形が喜久雄に言った「顔が美しすぎるがゆえにいつかその顔に自分が食われちまう」という言葉
同じく万菊の演じた「隅田川」がふたりにおよぼした影響
喜久雄が世話になる半二郎が冒頭の新年会にいて肚に一物もっていたとされるその理由(ここは推測になるかな)
上げていくとキリがないのですが
物語を作るうえでどれも重要となっています!
そして「誰を中心にみるか」で話の印象がかわるので、読んでいて何度も楽しめます。
喜久雄を中心に見ることが多いのですが、あえて俊介を中心にしてみたり半二郎を中心にみてみたりすると
感じ取れる事柄も変わってきます。
血筋として俊介が持っているものを喜久雄が欲しがり、その血筋があるがゆえに俊介の苦しみがあり
その喜久雄の血筋を実は徳次は欲しかったのではないかと思ってしまう(俺の想像ね)ような行動
この3人の最後の行く末がほんと気になります
2.最大のキーマン
話を進めていくと 喜久雄と俊介にはそれぞれキーマンになる人物が手助けをしていきます。
俊介の父であり、ふたりの師匠にあたる花井半二郎、のちにふたりに手ほどきをする万菊はその言葉でも重用な位置にいますね。また、興行をとりしきるやり手となった竹野も欠かすことができない存在になっています。
かれら無くしては、喜久雄も俊介もあそもまで大きくなる事はなかったので、周りには助けられたふたりですね。
あとは多数の女性も欠かすことができません。
なかでも俊介が世間から離れ落ちた時にだまって一緒に行動し、最後まで付き添ったアノ人は意外でしたがすごく重要な人間に育ってました。
一時これはそのまま世間から忘れ去られるのでは? と思ってしまうほど存在感がなかったのにビックリです。
徳次と弁天の動きもなかなか興味深いです。いつの間にか仲良くなったこのふたり、最終的にはそれぞれが別軸で成功していきます。その存在も見逃さないで見ておきましょう。
ほかにも多々キーマンがいるなかでやはり最大のキーマンは
辻村将生 です。
愛甲会の若頭(とはいえほぼ実権を握っていた)辻村のしたたかさと計算高さはビックリします。
ただこの人が花井半二郎に喜久雄をみせるきっかけを作り、その後も半二郎に世話になるように取り計らったおかげで喜久雄は芸の道に進むことになるので冒頭の新年会の出来事はいい意味でも悪い意味でも重用な局面でしたね。
その後も金の入り用な時には無条件に喜久雄を助ける事でも重要なひとです。
まあ 権五郎にとって最大の不義理をしてるんですけどね
とはいえ この人がいなければ後の喜久雄は確実に存在していません。
3.女性陣の強さ
登場する女性陣 ストーリー上この女性陣の働きが実に重要となってきます。
喜久雄の母親は新年会の余興として喜久雄と徳次に歌舞伎を仕込みますが、これが案外しっかりとした稽古で仕込んだことにより後々 花井半二郎の目に留まる事にもなります。
まずこの展開無くして喜久雄の人生が始まらないのでさっきでてきた辻村と同じくらい大事なトコです。
対して俊介の母親は家筋を重んじる梨園の母ながら俊介の身を常に案じています。
甘やかしていると思いきやここぞという時の判断は流石と言え、後半ガッツリ存在感が効いてきます。
同じく後半にその存在感を効かせてくるのが、15歳当時の喜久雄と一緒にいた春江で 彼女の行動はとても重要になってきます。
俊介も喜久雄も一緒にいる女性にかなり助けられますね。
俊介は 仕方ないかお坊ちゃんだもな って思えるのですが、喜久雄の方がいい感じでろくでもない事します。
結果的に悪い方向へ進まないのが話としては良かったですね。話の
今と違って昔は女性問題っておおらかだったよな と実際の出来事などをつい思い出してしまいました 笑
ともあれ 喜久雄・俊介共にさいごまで付き添ってくれた女性はとても重要です!
甘えや堕落を受け入れ進む道をともに行く春江も、愛情を利用されたと知ってもなお 寄り添う彰子も
すべて「役者」として自分の相手を生かしていくため。
今回の物語には強くてしたたかで芯のある女性が必須です。
4.こまかい描写が想像を膨らます
この小説 第三者が端から語る感じになっています。
その口調も「~でございます」みたいに少しかしこまった感じなんだけど、これがまた良い感じにハマってる。
歌舞伎自体あまりなじみがないのだけれど、ところどころにでてくる表現がてとも細かく綺麗なので情景が頭の中に広がってきます。
題目も結構な数でてきてますね。
「土蜘蛛」とか 知っているものもあるけど、ほぼほぼ知らない話ばかりです 笑
でも、ちゃんとそれぞれあらすじの説明がされているので読んでいる分には問題なく読み取れます
冒頭、新年会で乱闘があるのだけど ここの描写が悲惨なのに綺麗で、なんとも言えない感じをうけました。
浮かんだ景色が活劇っぽくて 狙いなら まんまとやられてます 笑
あと 演じてる役者自体の息遣いであったり、場の雰囲気、裏手の空気感などがすごく生々しくて好きでした。
なかなかあんな風に表現できないよ すごいよ
すごく歌舞伎が身近なものとして感じられる瞬間でした。
なにも知らなくても景色が想像できて楽しめるので、人間模様以外にも見どころがたくさんでした。
一番最初にでてくる演目が「積恋雪関扉」(つもるこいゆきのせきのと)。
演目名からして慣れないと大変そうでしょ? 笑
安心してください ちゃんとわかりやすく解説してくれています。
この演目が大元の始まりになるので、この章を読み終わったあと気になって坂東玉三郎さんの「積恋雪関扉」観ちゃいました!
今って便利ですよね 気になったら直ぐ観れちゃう!
これ 一度何かの演目をみておくと歌舞伎ってこんな感じなのねってわかるので、描写の細かさの伝わり方が変わってなおさら良い感じに読み進められます!
他の演目も後に伏線的にからでくる「隅田川」とか「道成寺」とかたくさんありますがどれも実際に観てみたくなってしまうくらい 気になる。
それくらい演目の描写が大好きでした。
特に喜久雄が求めた最高の「景色」の描写は何度よんでもたまらんです!
5.個人感想
全く違う世界にいたふたりがふとしたきっかけで一緒の道を進み、お互いに刺激を得ながら成長していく。
と書くと ありふれた話になってしまう 笑
そんな単純な話ではなく、ひとりひとり重厚に描かれています。
青年期から中年期にかけての嫉妬やドロドロした人間関係、あからさまな排除のやり方に各々が抱える苦悩など
もっともっと暗い話になっていても良さそうなのに どこか吹っ切れた感じがあって読んでいても嫌な感じを受ける事はなかったです。
それはもしかすると描写の美しさがあったのかも。
特に後半に行くにつれ芸が人間離れしれいく様(神格化って言われてた)や、だれもがたどり着けるわけではない高みにいつの間にか登ってしまった男の「孤独感」の描写はものすごく好きでした。
ふたりの男が長い人生のなでぶつかり合って得たものと失ったものは秤にかけられないけど
どちらもすごい生き方をしている話だった。
これってスピンオフ書こうと思えばそれぞれの立場で書けそうなくらい人物が豊富なので、見えない部分を勝手な想像で補って楽しんだりもできたので何倍もたのしめる本でしたよ。
まとめ
今回は吉田修一さんの「国宝」を読み下の5つの考察をしました。
1.誰を中心としてみるか
2.最大のキーマン
3.女性陣の強さ
4.こまかい描写が想像を膨らます
5.個人感想
普段触れる事のほぼない 梨園の話なだけに興味深々で読み進められました。
「舞台袖ってこんな雰囲気でこんな匂いなんだ」「役者さんって本番ギリギリで切り替えられるんだ」など身近に感じれるくらい細かく書いてくれていたり、梨園について「生き死にがかかった世界を、一丸となって生き抜いていかなけれいけない」などど華やかなだけではない裏側を真正面から書いたものなかなかないとおもいます。
これがもうすぐ映画化なんて
どんな内容に仕上がっているのかそれまた楽しみです!!
この本たちも面白かった!!
-
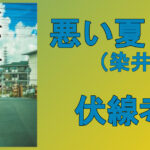
-
「悪い夏」(染井為人)の伏線考察
今回は染井為人さんのデビュー作でもある「悪い夏」を読んだのでおおまかな流れと伏線などについて解説します。今年(2025年)3月に北村匠海さん主演で映画が公開されますね、そちらも楽しみです!「悪い夏」で ...
続きを見る
-

-
「十角館の殺人」(綾辻行人)本格ミステリと言えば!
綾辻さんのデビュー作にして代表作「十角館の殺人」です。僕が綾辻さんを最初に読んだのは「眼球奇譚」なんですが、独特の世界観にガッツリとはまりまして 笑デビュー作からガンガン読んだのを覚えています。 もう ...
続きを見る